厄除けで人気の川崎大師は徳川家斉の祈願から人気が高くなった⁉
2025.09.16
2016.05.28
「上様の御成り。」で有名な大奥。江戸城本丸御殿に、この大奥がありました。
江戸城の「大奥」は、初代将軍徳川家康の時代から、その区画は存在していたそうですが、その頃はまだ形だけでした。政治の場と城主の私的な生活の場の区別がはっきりとしていなかったために、二代将軍徳川秀忠が「大奥法度」を制定し、このときから、政治と儀式の場所「表」、将軍の執務と生活の場所「奥(中奥)」、そして将軍の室と女官たちの生活の場所「大奥」と三つに区分されました。
この「大奥」のしくみは、豊臣秀吉が大阪城で、政治の場所と生活の場所をきっちりと分けていたことにならって考えられたものだそうです。
大奥の確立
この大奥法度をもとに、大奥を確立していったのは、三代将軍徳川家光の乳母である春日局です。
徳川家康にはたくさんの側室がいましたが、御錠口(おじょうぐち)という杉の戸を開け、鈴の音を鳴らし、「上様の御成り。」と御鈴廊下(おすずろうか)を将軍が歩いていくという光景は、徳川家康のときも、秀忠のときもなかったことなのです。
(この辺りが大奥のあった場所)
(同じ場所をお城があった外側からみた様子)
徳川家繁栄のため、世継ぎを絶やさないためにも、子どもを産むということが最重要となる将軍の正室ではありますが、当時は政治的策略のもとの輿入れになりますので、気持ちが合わず、正室とは仲睦まじくなれない場合もあったようです。それでは困るので、側室を持ち、世継ぎが誕生することを願ったということになるわけです。
側室が男の子を出産すると「お部屋さま」と呼ばれるようになります。その子が時期将軍となった場合は、側室でも将軍の生母ということになり、御台所よりも権力も権威もはるかに高くなります。そのため側室たちは将軍の寵愛を受けるために、必死になり、熾烈な戦いを繰り広げることになってしまったようです。
そのような女性の戦いに辟易してしまう感もありますが、当時、自分の意にかかわらずに、大奥に上がることになってしまった女性にとっては、自分の価値を実感できる術が他になかったのかもしれないと考えると、同性としてはとても切ない気持ちになってしまいます。
側室の中に、将軍のお目にかなわなくとも、将軍の生母にならなくとも、大奥という御殿で優雅に暮らせることだけを楽しむという女性がいたとしたらいいのに・・・と思うのですが、いかがでしょうか。
その場所は、江戸城跡に木立の中にひっそりとその場所を知らせる立て看板だけが残ります。
皇居 東御苑 東京都千代田区千代田
東京メトロ 大手町駅
開苑時間 原則として月曜日と金曜日以外の各日
午前9時~午後4時45分(4月15日~8月末日)
午前9時~午後4時15分(3月1日~4月14日、9月1日~10月末日)
午前9時~午後3時45分(11月1日~2月末日)
入苑は閉苑の15分前まで。
入場無料

rico
教育系ライターricoです。 公立小学校の教員をしていました。戦国時代の強い姫たちが好きです。特に江のファン。読んでくださる方の心にイメージが広がるような文章を紡いでいきたいと思っています。
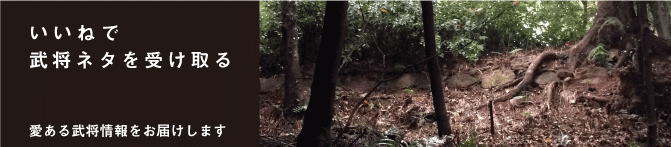
関東地方の記事
徳川家康の記事
この記事の後によく読まれているおすすめ記事
バックナンバー記事
この記事へのコメントや情報提供をお待ちしています